【コラム】Travis Scott 『UTOPIA』| 『Circus Maximus』を通して

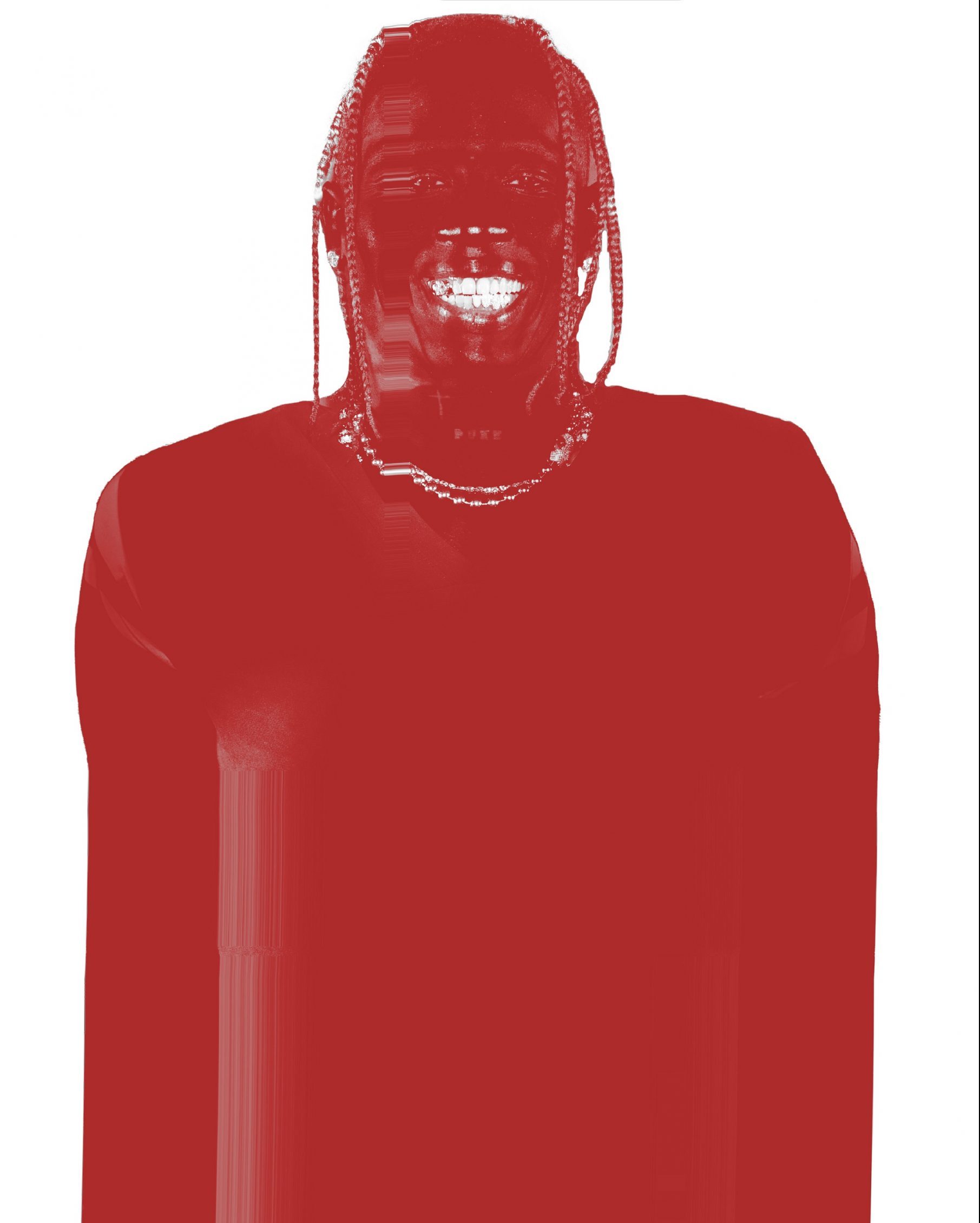
2023年7月28日、Travis Scottの通算4作目のアルバム『UTOPIA』がリリースされた。また、その前日には、前作から5年ぶりとなるこの新作に先がけ、 北米のAMC系のごく一部の映画館で、アルバム収録曲のひとつと同タイトルの映画『Circus Maximus』の上映が始まった。そして、8月7日には、楽曲と映画のタイトルとなったイタリアはローマにある、今から2000年ほど前には、実に30万人(!)もの観客を収容する能力があったキルクス・マキシマス(Circus Maximusのラテン語読み)」で、ライヴが行われる。
となれば、『UTOPIA』を聴く上でのみならず、そのタイトルから考えても、映画『Circus Maximus』は、彼の活動の根幹を成すライヴでの活動展開を占ううえでも大きな意味や関係を持っていてもおかしくない。なによりも映画の総合監督がTravis自身なのだ。
そして、映画は思わせぶりたっぷりで始まる。アイスランドの氷の洞窟の奥で、Travisはいきなりクラーケンのようなタコの化け物と邂逅するのだ。触手を伸ばし絡んでくるタコに彼は特に抵抗しない。様々な方向に触手を伸ばすこのタコは、妄想のなかの彼自身の姿なのかもしれない。また、映画『ファイト・クラブ』で瞑想中の主人公が氷の洞窟で目にするペンギンのような「パワー・アニマル」と考えることもできそうだ。
次に彼が訪れた邸宅の庭で待っていたのは、かのRick Rubinだ。映画ではこの二人の対話場面は、黒いスクリーンの中央部を(ひとつ)目のかたちにくりぬいた、その内側の部分しか見えない画面に映し出される。これを見て、2019年のコーチェラで配信されたSunday Serviceの画面を思い出す人もいるだろう。あの時は、画面の中央にくりぬかれた円形を長時間見つめたのだった。Kanye(作品)への目配せは『UTOPIA』では、実に四曲で行われている。今から10年ほど前にSoundCloudでTravisを初めて聴いた人たちの多くの動機は、Kanyeにそっくり、との噂の確認だったはずだ。当のKanyeは無視するどころか、フックアップしたところから彼のキャリアは軌道に乗ったのだし、RubinはKanyeのアルバムをプロデュースしている。
そのRubinは、あたかも天啓を授けるかのように、ラップアーティストから創作上のパワーを引き出すことで知られているが、「あの悲劇以来まだ悲しんでいるのか」「子供は元気か」と、ここでは第一声から妙に俗っぽい。対するTravisも「そういうことを話しに来たわけではない」とすげない。
悲劇とは、2021年の11月5日の夜に、地元ヒューストンでのアストロワールド・フェスティヴァルで開かれた彼のライヴの最中に一部の観客が突如ステージ前に殺到、それに巻き込まれた観客のうち8人(最終的には10人)が死亡、さらに300人ものの負傷者が出てしまった出来事のことだ。
このフェスを立ち上げたのがTravisなら、事故発生時にステージに立っていたのもTravisであり、責任は彼に重くのしかかった。集団訴訟が起こされ、ヘッドライナーが計画されていた翌年(2022年)のコーチェラへの出演もそうした重圧により、キャンセルされた……。
そこからの復帰第一作となれば、出発点となったKanye作品との関係性をなんらかのかたちで表現したいと考えてもおかしくない。まず、"Black Skinhead"で聴いたドラムが聴こえてしまうため、一聴しただけで、どうしても記憶に残ってしまう曲に"Circus Maximus"と名づけている。ローマ帝国のキルクス・マキシマスでは、戦車競走をメインに、野獣狩り、はては人間対猛獣のような血腥い見世物が行われていた。"Black Skinhead"が、当時のカニエに対する悪評へのフラストレーションから生まれたことを思い出せば、ここでトラヴィスが自らを敢えて超大観衆の見世物として差し出す理由も見当がつくだろう。そして、「Donda」収録曲として制作が始まったと言われる"God's Country"、"Thank God"、"Telekinesis"の3曲は、楽曲がカニエとのあいだを行き来するうちに熟成されていったようにも聴こえる。
映画『Circus Maximus』は、RubinとTravisの対話のあいだに、『UTOPIA』収録の計4曲のMV(ニコラス・ウィンディング・レフンやギャスパー・ノエによる監督作を含む )を挟むかたちで進んでゆく。
そのうちの2曲目にあたる"SIRENS"のMVには、悲劇後に彼が悟ったことが描かれている。そこでは、はてしなく上にむかって続くような人間ピラミッドが映し出される。Travisもそのなかのひとりで、重圧に耐えながら踏ん張っている。その横を通って、子供が上へと登ってゆく。てっぺんには穴が空いてそこから外界(明るい未来)に出ようというのだろう。
ここでもしもTravisがバランスを崩せば、ピラミッドは崩れ、子供の未来も断たれ、多くの負傷者が出てしまう。Rubinとの対話で、彼はバランスの重要性を強調する。自身の最新作の「UTOPIA」と、俗に言うユートピアとの違いをこう説明する。「いたるところが綺麗だとか、対立がない、とかそういうのではない。対立を考えたときにバランスをどうとらえるのか」。これは自身がキャンセルの対象にされ、身をもって経験した極端な力の不均衡に無関係だとは言えないだろう。アルバムでは"DELRESTO (ECHOES)"でBeyoncéと共演しているが、例えば、彼女のファンの中には今回の共演後であっても彼のキャンセルを主張してやまない者が少なくない。
だからといって、Travisがバランスと言う場合、対立そのものを否定しているわけではないし、五分五分で均衡がとれた状態だけを理想(つまりUtopia)としているわけではないはずだ。それには、彼の音楽がもたらす効果を思い出したらよい。彼がよく口にする言葉にrageがある。これは本来、抑えきれないほどの怒り、を意味する。それを彼は、はっちゃけること、あるいは、身体の内側に溜まった悪いエネルギーをすべて吐き出し、新鮮で良いエネルギーを吸収すること、というニュアンスでとらえているのだ。そこから、彼は自分の熱心なファンを rager(s)と呼んでいる。それでも、バランスとrageは、あまり相性がよくなさそうだ。Travisは「新しいかたちのrageを見いださなければならない」とRubinに話す。「いつまでも待ってられない」そう言って彼は対話を切り上げ、その場をあとにする。
続いて、映画は、そこがイタリアのポンペイだとわかるショットをいくつか重ねてゆく。そこに、『UTOPIA』の1曲目に収録されている"HYAENA"が流れると同時に、カメラはTravisの姿を捉える。どうやらそこは、ポンペイの野外円形闘技場の一番高い場所であるようだ。彼はそこからすりばち状の劇場の底の舞台にあたる場所(特にステージがあるわけではない!)までせわしなく降りてゆくと、マイクを拾い上げる。その瞬間に、Travisの姿よりも目を引くのは、彼の背後にそびえ立つ、積み重ねられた真っ黒なスピーカー・キャビネットでできた山だ。その高さは彼の身長の三倍も四倍もある。いったいどんな音を出そうというのか。
彼ほどではないにせよ、1971年、まさにこの屋外円形闘技場で、同じように不釣り合いなほど数多くの黒いスピーカー・キャビネットをステージ後方に並べてライヴを行なったアーティストがいた。UKの4人組ロックバンド、Pink Floydだ。その模様は、『ピンク・フロイド・ライヴ・イン・ポンペイ』として映画に記録されている。そして、彼らがおこなったのと同じように、Travisのライヴも無観客でおこなわれた。加えて、そのライヴが、太陽の出ている時間帯から夕暮れ時を経て、夜まで続いたかのように編集されているところまで同じだ。Adrian Maben監督は、『ピンク・フロイド・ライヴ・アット・ポンペイ』を無観客で撮った理由について、グループのロシアのファンサイトでこう説明する。「あの当時、コンサート映画にうんざりしていた。要は、反『ウッドストック』映画を作るというのが、あの作品の大きなアイデアだった。誰もいない、あるのは音楽と静寂、そして、空っぽの屋外闘技場、そっちのほうが、何万もの観衆以上ではないにしても、大きな意味があるように思えた」
Travisにとっても無観客ライヴは大きな意味があるが、その意味合いはまったく違う。まず、フェス(映画)へのカウンターではなく、フェスに拒絶されてしまったのだ。そして、あの悲劇後のリスタートなれば、まずは無観客で、というのがしかるべき選択なのではないだろうか。Travisへの集団訴訟が最終的に断念されたのは、2023年6月29日になってからである。
無観客のポンペイでも彼は、4曲目の"MY EYES"でスピーカー・キャビネットの山をよじ登り、そのてっぺんに腰かけて、マイクを握る。「俺が再生するのはあの夜のこと、俺のいる場所から、俺の目に見える人の海、しっかり俺についてきてくれてる。あのみんなに知っていてほしかった、このスコッティなら、ステージから飛び降り、あの子供を救うためなら力を尽くした、と、俺が作り上げたものがすっかり重みを増している。それとうまくバランスをとって、自分の目を覚ましていかないと」
続く5曲目の"GOD’S COUNTRY "では、その場に立ち上がる。本来ならそこで観客に大声で呼び掛けたいところだろう。だが、そこには観客はひとりもいない。「Pompeii」と題された、このライヴのパートを撮ったのは、ハーモニー・コリンだ。この監督が2012年に撮った『スプリング・ブレイカーズ』は、Jackboysのヴィジュアル・イメージに大きな影響を与えている。また、2023年9月のベネチア映画祭に出品された監督による新作『Aggro Dr1ft』では、Travisが主演の一人を務めている。そんなコリンがこのライヴで作った画面は、無観客ライヴだからといって、ここぞとばかりに被写体を接写したりはしない。逆に、どちらかといえば、カメラは、Travisとはほぼ一定の距離を保っている。Travisの頭上近くを浮遊しているドローンからの主観ショットくらいしか彼に近づかない。むしろ、いかにもドローンで撮ったようなショットは、逆に観客と被写体との間に広がる距離を強く意識させてしまう。この妙な「近づけなさ」は意図されたものなのだろうか。
思えば、Travisとの距離は、彼が『Rodeo』でアルバム・デビューを果たした2015年から早くも問題視され、大きな課題となっていた。ライヴ中に、観客にセキュリティを無視してステージに近寄るよう煽り、罪に問われ、その二年後にも同様の案件で逮捕されている。ragersは彼に煽られれば当然、そうでなくともモッシュピットやダイブで自分自身から積極的に盛り上がり、会場の熱狂を高めていた。
一方、ポンペイでは陽が暮れかけると、例のドローンが光源となり、頭上からステージ上の彼を照らし、引きの画では、彼の全身像が夕闇や夜の中で浮かび上がる。ここではこれがメインの照明なのだ。他に、闘技場の観客席のあちらこちらに太陽光発電のパネルのような光源を設置し、夜空に向けて光を放ち、それをステージの、いわば間接照明として使ったりもしている。そんな調子なので、画面は基本的に暗く、ギタリストとドラマーが(遠隔操作された)ロボットであるのに気づくまで時間がかかるかもしれない。こうした「近づけなさ」や「見えにくさ」は、この作品固有の表現手法なのか、従来のTravisのライヴへの飢餓感を募らせるためのものなのか。
とはいえ、ここはここで、例えば"FE!N"では、オリジナルのPlayboi Cartiに替わり、Sheck Wesが客演し、ラストの"TIL FURTHER NOTICE"では、イントロで歌い出すのはオリジナル同様James Blakeでありながら、キーの違いから別録りヴァージョンであることが判明したりもする。
こうして『UTOPIA』のリリースを経て、キルクス・マキシムス公演を迎えることになる。当初はアルバムの発売日である28日には大ピラミッドのあるエジプトのギザでの公演も予定されていたが、急遽延期となった。キルクス・マキシムス公演を伝えるポスターにはこう書かれている。「ユートピアとは、それがどこであれ、いまあなたがいるところにある」。Travisは5月にXXLでこうも説明している。「ユートピアとは、到底信じられないとか、到達できないと人が感じるような、完璧な精神状態のことだ。でも、それは自分で創り上げることができる。ユートピアを獲得する人は毎日出てる。それはサイコーにドープな家を持つ超リッチな人たちとは限らない。ユートピアとは、あなたがたとえどこにいようと、手に入れられる最高のもの」
もしかしたら、それが「新しいかたちのrage」なのだろうか、YouTubeにアップされたキルクス・マキシムス公演を見て真っ先に目に飛び込んできたのは、ステージセット。ここでは、スピーカー・キャビネットの山がさらに大きく高いものとなっている。映画『Circus Maximus』は、Travisのキャリアにおけるクッションなのか、はたまたスプリングボードとなったのか。公演当日の夜、会場周辺の住民から、役所に地震の発生を確認する電話が数多く寄せられたという。どうやら、その時刻は、Travisのステージに、反ユダヤ発言以来初めて大観衆の前にYe FKA Kanye Westが姿を現した直後で、興奮した大観衆の足踏みが近隣を地震のように揺らしたことが原因だとみられている。(小林雅明)
Info

Travis Scott
New Album『UTOPIA』
デジタル・アルバム&輸入盤発売中!



