URBAN ART RESEARCH Vol.1 | Houxo Que 『Proxy』

「暮らしは素早く変わる/暮らしは一瞬のうちに変わる/夕食の席についてそのとき、あなたが馴染んでいる暮らしが終わる」
ジョーン・ディディオン/The Year of Magical Thinking (拙訳)
なぜなら彼が様々な領域を跨って活動してきた過去があるゆえだが、コンテンポラリーアーティストHouxo Queは、何回もの「同化と異化を繰り返し」(東京都現代美術館学芸員薮前知子氏によるHouxo Queへの評より)ながら、そのキャリアを拡げてきた。東京は秋葉原の近くに位置する、小学校の建築をアートセンターへと変貌させアーツ千代田3331の2FのギャラリーOUT of PLACE TOKIOで個展『Proxy』を開催中の彼が扱うのは、メディアとしての「液晶ディスプレイ」だけなのではなくその「死」でもある。
ストリートアートやライヴペインティング、コマーシャルなデザインまで幅広く手掛けてきた彼は、2011年以降、人工的な発光をするディバイス=液晶ディスプレイを使って現代美術の領域で活動をしてきた。アートの中心的な形式の一つである視覚芸術、なかでも伝統的な絵画と、コンテンポラリーな存在である私たちが多分生まれてから死ぬまで囲まれる無数のディスプレイやモニターと呼ばれるテクノロジーの産物/オブジェクトを、彼は結びつけざるを得ない。
2020年代の都市の新しいアートを考える、『URABN ART RESEARCH』の連載の第1弾として、Houxo Queに登場してもらう。
取材、執筆:荏開津広
撮影:寺沢美遊
編集:高岡謙太郎
カルチャーに沈殿した思春期
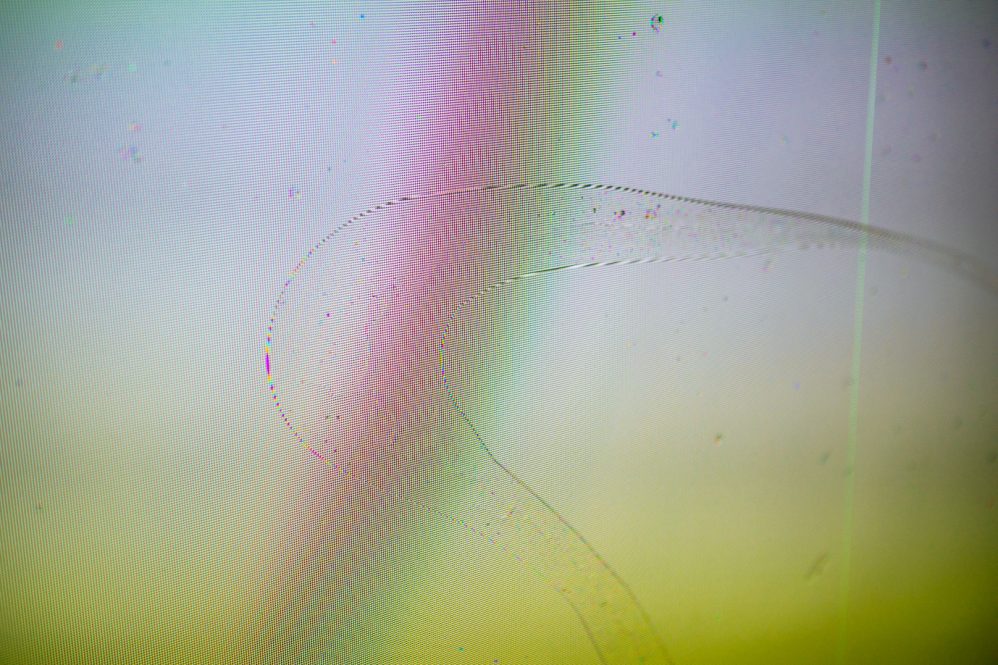
美術についての記憶について教えてください。
「母は建築のイラストレーター、離婚した父も日本画家だったんですね。本当に子供の頃、2、3歳ぐらいの記憶として父のアトリエを見ていたりとか、母が美術を好きだったので、家にあったパウル・クレーやダリの画集の見ていたりとかが美術に触れたその始まりだったと思います。」
Queさんがファインアートへの興味を持つのは幼い頃からとして、日本に生まれ育つとサブカルチャーに触れる機会は多いのではないでしょうか?
「叔父が20歳上のガンダム直撃世代で、そこからスカルプチャーに興味を持って今はインダストリアルデザイナーという人なので、“ガンダムはいいぞ、AKIRAはいいぞ”と布教がありました。彼がウチから美大に通っていたので、その頃彼のコレクションのオモチャとか絵とかアニメとか盗み見させてもらって育って、気がついたらズブズブのオタクになっていました(笑)。OVA(オリジナル・ビデオ・アニメ)をいっぱい観て『コンプティーク』というPCゲーム雑誌を読んだり、恋愛シミュレーションゲームに興奮してという世代です。僕が中学生の時にテレビで『新世紀ヱヴァンゲリヲン』の放送が始まって、碇シンジと同じ14歳で、あれはデカかったです。中学2年生ってメンタリティが鬱屈していると思うんですが、そこにあの『エヴァンゲリオン』の暗い感じがきれいに滑り込んできて、自分の人格形成と深く癒着してしまって……中学の時は通学の途中に歩きながら、声優の林原めぐみとか椎名へきるとかのラジオ番組を録音したものを聞いていたので……当時どこにでもいるようなフツーのオタクでした(笑)」
都市空間が生み出した作品に気付く

その後、美術予備校から高等美術教育を受けるという日本のコンテンポラリーアーティストが通過する通常の教育の手続きの途中で、世界でも有数の巨大な都市、東京の傘の下で育ったHouxoは、「もうひとつのアート」ことストリート・アート/グラフィティの洗礼を受ける。
「地元の駅のプラットフォームから見える壁に、あるグラフィティライターが大きなレターを書いていたんですよ。めちゃくちゃかっこいいな、と思ったんです。自分が当時学んでいたものよりもっと自由で、かっこいいものをやっている、この人たちは、と思いました」
もっとも、幅広く美術とコンテンポラリーアートの面白さや可能性に無頓着・無関心であったわけではない。
「例えば、ストリート・アート/グラフィティの世界にいた頃も、東京都美術館で狩野探幽の展示(2002年)をやっていて、狩野派、滅茶苦茶かっこいいじゃん、と思いインスパイアされたり。それ以前、僕が通っていた予備校は受験する美大の学科に狙い定めてカリキュラム組む受験対策バリバリではなく、かなりノリで指導しているフシがある(笑)ところでした。デッサンの授業とかは映像を目指している友だちとかはともかく、かったるいから課題のために置いてある石膏像を持って近所のゲーセンに行って石膏像のプリクラ撮って課題を提出してすごい怒られる人とかいて、『あ、こういうのアリなんだ』と思いました(笑)。そういうところは色々学ばせてもらったと思います(笑)」
——とは冗談としても、彼は、美術とオタクとストリートアートの世界へ飛び込こむということなどの間に峻別があったわけではないという。
「ストリートアートもアニメも、僕の場合には何かを一つ選んだときにその前に選択されていたものが上書きされてなくなるということがあまりなくて、トピックが増えていく。“このスレッドは残して、新しいスレッドを作る”ということで、絵画への関心、アニメへの関心、グラフィティへの興味も持続している。ただ、そのときにやりたいことへそれまで意識的にも無意識的にも抽出してきたエッセンスをそこのなかへ流し込んでいるという感覚はあります」

私たちが着陸する機内から地上を眺める際に理解できるように、都市とは遥かに巨大な光の集合体である。ならばストリートアーティスト/グラフィティライターはその光の集合体へダイブし潜入し、陰になっている場を活性化させていく存在ともいえるだろう。
「ストリート・アーティスト/グラフィティ・ライターというのは単にそのフィールドが巨大で街もそのなかに入っていて、だから街にいるときは当然警戒しているという面もあるんですが、ある種リラックスしている面もあったかと思います。それは、自分が知っている場所にいるという感覚です」
震災以降ディスプレイと対峙するように

2000年代を通してストリートでの表現からクラブでのライヴペインティングを通し企業コラボレーションへと旺盛に活動していた彼は、2011年の3月11日もライヴ・ペインティングのイベントを依頼されていた。
「3.11には、東京は六本木ミッドタウンでライヴペイントの予定があって、それに向かっていったところでした。ウチから車で出発してちょっと走り出したくらいに揺れて家に戻ったとき、テレビで三陸沖が津波に呑まれていく映像をリアルタイムで中継しているのを見ました。映像のショックのなかその後も日本中が自粛ムードが続いていたのでインターネットを見続けました。でも、ある時ふっとディスプレイを見続けている自分を客観的に見て、近所の壁が崩れたりしても被害は軽微だし、身近に被害者がいるわけではない、ましてや被災地の当事者でもないのにショックを受けている自分……これはなぜだろう? 写真や(紙の)新聞を見ても自分はこうならないよな?と思い、そこから手探りを始めました」
言うまでもなく、東日本大震災は少なくないアーティストたちに後戻りのできない影響を残した。その年にアーティスト小森はるか+瀬尾夏美は東北沿岸に移住し、彼女たちの暮らしと人々の日々の営みのみならず、実に木々に花に森にその土地さえもアートと分かち難くなった。
一方で、私たちの意識と身体を否応なく変えたあの日と映像=光の関係を突き詰めていった試みが日本のコンテンポラリーアートの領域にも顕れた。例えば、差し迫った状況下だからこそ映像と権力についてラディカルに詰問した『指差し作業員(代理人竹内公太、2011年)』。もしくは黒い笑いのパフォーマンスのドキュメンテーション『気合い百連発(2011年)』。ちなみに後者のChim↑Pomはモニターを通してHouxo Queが2011年に目撃した爆発の光景のみならず、もう一つ忘れられない1945年の人工の光に関連した作品を制作している( “ピカッ”、2008年)。
ディスプレイをメディウムに

「まず最初に始めたのはディスプレイで見たいものを見るだけではなく、見たくないもの、自分からは見ないものを見続けてみる。ディスプレイを通して他人と関係する場としてネットゲームをハードコアにプレイをして深く没入してみたり。ディスプレイは光っているもの。だから光と色について学んでみようとゲーテ『色彩論』とニュートンの『光学』という対立した主張を比較しながら読んでいく。そうすると次は比較の中で、光とそれを知覚する身体について関心をもっていって、友人から紹介してもらったSYNAPSEという東大の研究者を中心としたグループと出会い、彼らから研究について教えてもらったりして、目と脳の関係について学んでいきました。その中でゲーテの主張を認知表示的な色、ニュートンの光学的な色と分類し、そこから光が過去の文化の中でどのように扱われていたかなどについて調べていきました。そこでは当然、絵画や写真といった表現に出会いますし、古代まで遡れば神の象徴といった超越性へとつながります。それは光というテーマを美術史を通して学ぶことでした。そして、改めてディスプレイを見直してみれば、その形態は絵画に限りなく近いものでした。少し話が逸れますが、CBCNETの栗田さん主催のBYOBというイベントに参加した時に、同じく参加していらっしゃった長谷川踏太さんがおもしろいエピソードを話してくれました。それは、昔、長谷川さんが柳宗理さんにプレゼンテーションをしようとディスプレイで作品を見せた時、柳さんはディスプレイの縁を触りながら『これ、なんの素材?』と訪ねたというエピソードでした。そういった素朴な眼差し、ディスプレイをモノとして見るような態度に感銘を受けたのを覚えています。そうして、ディスプレイの構造を調べたりしていって、絵画の支持体としての”板”であるディスプレイを発見したように今振り返れば思います。最初にディスプレイを取り入れた作品を制作したのは2012年で、発表したのは14年です。まずは直接ディスプレイに絵を描きました」
しかし、先ほども記した通り、チャットルームに残してあるスレッドのように、Houxo Queにとってアニメもストリートアートも「現代美術」に到達するための途中経過ではない。そのことは或る種「整理されていない」という彼の作風と関係もあるのだが、幾つもの言語(そのすべてを理解できるかどうかは別としても)が飛び交う空間の裡に彼が育った時間と関係があるという。
「当時もストリートアートへ美術を導入することを強く意識していたのではないし、僕は滅茶苦茶ごちゃ混ぜかも知れません。ストリート・アートの部分、サブカルチャーの部分、ファインアートな部分、メディアアートの部分、やたら要素が多いのですが、自分でも整理出来ないからどうしようもなく出していってるというところもあるし、既存の文脈にノレないのはハンディキャップにもなって必ずしも良いことではないと自分でも思います」
それは「子供の頃から家庭環境での国籍が違い、話す言葉も違うしそれぞれが属している文化も少しづつ違う、でもそれを何かに統一したりしないという意味でバラバラにやってきた環境が身についている」という多元的な言語と振る舞いがクロスする空間の内面化かも知れないのだ。
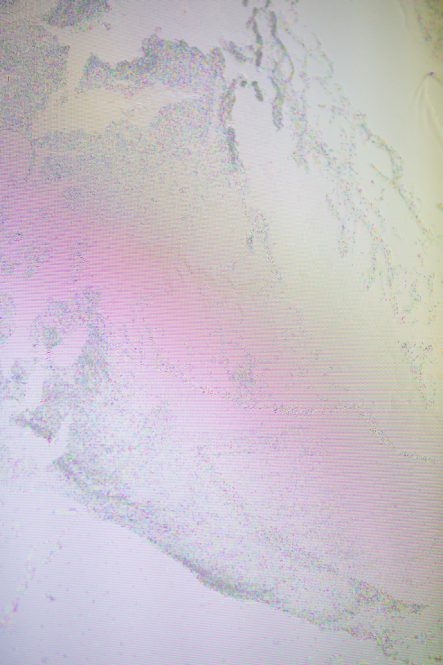
「先程もお話しましたが、光の作品を作るうえで、光を一番古くから扱っている分野は宗教なので美術史を参照したりしながら宗教について調べたりもしました。歴史的には、人が超越的なものを見るときにそこに光があるからといって、毎日液晶ディスプレイの光を見ているオレたちは超越的に生きているといっていいのか、とか。(実際は)極めて世俗的に過ぎない――でも(自分たちはディスプレイからの人工の)光を浴びて生きている」
2020年、個展『Proxy』では、2011年に「あそこでそれまでライヴペイントで描いていたようなものを同じように描くことが出来なくなった」Houxo Queの手により、破壊され終わりつつあるようであるオブジェクト=ディスプレイは制度自体の破壊と終わりへと私たちを導いていく。それは、ここで強調したような2010年代の日本が経験した物理的ないしは心理的損傷のプロジェクションのみならず、実に様々なレベルのありようを開示すると同時にその終わりを示唆する。
1962年にSONYがポータブルヴィデオカメラを開発して以来ヴィデオモニターが日本/アジアのアートの特長に付け加えられていった歴史にも、ギャラリーの空間に踏み入れた鑑賞者は立ち会うことになるだろう。しかし、オブジェクトの一つは破壊され、定期的に、繰り返し、明滅している。その単管が突き刺さったディスプレイが上からギャラリーの空間を見下ろしている。横たわったディスプレイ、壁に立て掛けられたもの、ブラックライトに照らされた小さなコト・モノ――「事故のようでもある、意味に取り巻かれていない、重要なのは死んでいるという事実」という作者の言葉は、空間をいかに経験するかに関わってくる。
グローバル・パンデミックが現実となり、国境が閉じ、口汚い人種差別が倫理に代替された時代に、古い制度が破壊された後、新しい美しさへと想いを馳せる古典的な美しさを起動させる装置に、ディスプレイは変貌していく。
Houxo Que氏よりコメント(2020年3月26日)
「今の人類社会はグローバル資本主義によって人やモノ、コトの移動が加速され続けています。COVID-19の各国での流行はまさにそのコインの裏でしょう。英国のボリス・ジョンソン首相が外出禁止令に合わせて発表した談話では、“Invisible killer”(見えない敵)という言葉が強調されていたのが印象的です。しかし、Virusは本当に『見えないもの』なのでしょうか。コロナウィルスはその姿が太陽のコロナ(光輪)に似ていることがその名前の由来となっており、顕微鏡を覗けばそれは『見えるもの』です。その意味ではジョンソン首相のレトリックは、極めて身体的な視覚認知のレベルに寄り添ったものであると言えるでしょう。そして、その『見えないもの』を〈見る〉時、我々はまさに現実の事象と重ねながら想像力を駆動させて恐怖してるのではないでしょうか。
この状況では皮肉なようにも感じますが、自分のディスプレイの作品はその逆で、見えているはずなのに『見えないもの』であると考えています。ディスプレイは世界の滑らかな動きを再現するために、(一般的なものであれば)1秒間に60回の変化をし続けます。しかし、その速度は私達の認知表示とっては瞬間を見落としつづけさせる光の痙攣でもあります。つまり、ディスプレイ上に表示されるすべてを私達は光としては浴びてはいても、それは『見えない』のです(そして、この光る端末を通して表示されるネットワークなくしてグローバル資本主義も成り立たないでしょう)。週末の外出自粛要請(“自粛”を“要請”などというのは、まったくふざけた言葉だ)が東京都知事が会見で述べた今、私達は『見えないもの』への想像力を、それがどのような姿であれ、実践的な場面として問われている局面に差し掛かっているようにも思います。しかし、では『見えない』とはなんなのでしょうか。またそのコインの表である『見える』とは、それほど確かなものでしょうか。私はこのように考えます。それらは、私達が連続性をもって世界を表象する機能によるものであり、そこで用いられる想像力によっていかようにも回転するコインの表裏であると。であるならば、まず私達自身の〈見ること〉の限界と不可能性を知るべきではないのかと考えており、自分の作品がその一助になるのではないかとも考えております。
また28・29日は“要請”を受けたのでギャラリーは閉めています。延長した日程にもし間に合えば是非。ですが、まずは健康を第一に。手洗いと消毒を忘れずに」

Info
Houxo Que”Proxy”
会期: 2020年2月21日(金)- 2020年3月29日(日) 会期延長 2020年3月31日(火)(但し3月28日(土)、3月29日(日)は休廊)
会場:Gallery OUT of PLACE TOKIO
HP:http://www.outofplace.jp/tokio/
Houxo Que
http://www.quehouxo.com/

