【レビュー】三浦大知『球体』の衝撃 | 新たなリスナーにまで訴えかける、ポップスの傑作

三浦大知が7月11日にリリースしたニューアルバム『球体』が話題を呼んでいる。世界的なモード――すなわち、アンビエントR&Bであるとか、あるいはEDM以降のダンス・ミュージックを消化しきったうえで、日本語のポップスとしての高い完成度を見せつけた本作は、三浦大知の底力をリスナーに再確認させるに充分な傑作だ。その衝撃は、彼の活動に注目してきたリスナーだけではない、新たなリスナー層にまで及んでいる。
表現の可能性を追求した作品
本作がユニークであるのは、そのポップスとしてのクオリティの高さだけではない。『球体』は、アルバムのリリースに先駆けて開催された、演出・構成・振付までを三浦自身が手がける同名の公演までを含めた、総合的なパフォーマンス作品でもある。既にそのパフォーマンスを生で体験することはできないが、CDに添えられたBlu-ray/DVDには、そのステージの模様が特別に収録された映像が収められている。80分近くに渡って、ステージ上をたったひとりのパフォーマンスで支配する三浦の姿は、楽曲の提示する世界とあいまって、見る者に鮮烈な印象を残す。
三浦は、1997年、Folderのメインヴォーカルとしてわずか9歳でキャリアをスタートした。そして、変声期に伴う活動休止を経た2005年のソロデビュー以来、ことヴォーカルとダンスがわけられがちな日本においては稀有な、「歌って踊れる」男性ソロアーティストとして独自の道を歩んできた。それゆえ、彼が自分の持つヴォーカルとダンスのスキルを思うままに発揮し、自らの表現の可能性を追求した一作として、『球体』はとても意義深い。
また、本作のリリースは、メンバーである橘慶太のプロデューサーとしての評価も高まるw-inds.や、「U.S.A.」を発端とするSNS上のバズを通じて再び脚光を浴びたDA PUMPといった、キャリアを積んだ男性ヴォーカルダンスグループの活躍がめざましい昨今のJ-POPシーンのメルクマールであるとも言えよう。それは同時に、洗練された歌とダンスを武器にグローバルな舞台で存在感を見せる、BTSをはじめとしたK-POPアイドルとの、すぐれた同時代性も示している。
とはいえ、注意しておきたいこととして、三浦本人のパフォーマーとしての実力の高さはもちろん、トレンドをおさえた質の高いサウンドプロダクションもまた、これまでの彼の活動に一貫するものだったという事実がある。じっさい、『球体』で全面的にタッグを組み、作詞・作曲・編曲までを一手に担った本作の最重要人物、Nao’ymtは、ゼロ年代末からたびたびコラボレーションしてきた、三浦のキャリアを語るうえでは欠かせないプロデューサーのひとりだ。R&BヴォーカルグループJineのメンバーとして、セルフプロデュースながらオーセンティックで良質なR&Bサウンドを送り出し、ゼロ年代以降の安室奈美恵の躍進を支えるプロデューサーとしても腕を鳴らしてきたNao’ymtは、三浦のシングル曲やアルバム収録曲を数多く手がけている。
また、近年の三浦は、アンダーグラウンドなシーンとのコネクションを積極的に築いてきた。直近のヒット曲である2017年リリースのシングル"EXCITE"では、若手プロデューサーを多数抱えるTREKKIE TRAXからCarpainterを編曲に招き、特撮モノ(『仮面ライダーエグゼイド』)の主題歌にふさわしいアップテンポな楽曲にジャージークラブのエッセンスを散りばめた一曲を仕上げているし、2016年には唯一無二のサウンドとパフォーマンスで日本のエレクトロニックシーンを代表するプロデューサー、Seihoとのコラボレーションでシングル"Cry & Fight"をリリースしている。
このように、三浦がキャリアを通じて積み上げてきた信頼と実績の延長線上に成り立つ作品として『球体』という快作はある。前置きが長くなってしまったが、そのことを確認したうえで、本作を掘り下げていきたい。
アンビエントとハイファイの両立
『球体』に反応した三浦大知のファン以外の人びとの多くは、アンビエントR&Bや、チルアウト寄りのダンス・ミュージックといった、アメリカを中心としてグローバルなトレンドとなったサウンドとの同時代性を本作に見出している。その傾向をひとことであらわすとすれば、豊かな空間を感じさせるアトモスフェリックなサウンド、ということになるだろうか。ドライでエッジの立ったサウンドというよりは、深い残響の海に聴き手をいざなうような雰囲気をたたえた音作りが、『球体』の第一の特色だ。
たとえば"淡水魚"や"対岸の掟"といったバラードは、伸び縮みしてゆらぐビートと、リヴァーブのなかに漂う電子音の絡み合いが、三浦の流れるような歌声ともに、現実離れした空間を体験させてくれる。とりわけ「淡水魚」は、ファルセットと地声を行き来するスリリングなヴォーカルが、空間の深さに緊張感を加えている。
ただし、しばしばローファイな録音をコラージュ的に取り入れるアンビエントR&B――Frank Oceanの『Channel Orange』や『Blonde』がその筆頭だが――に対して、『球体』は一貫してハイファイで、クリアな音像を維持している。私見ながら、前述したFrank Oceanの諸作や、あるいはSolangeの『A Seat at the Table』といったアンビエントR&Bを代表する作品は、私的で親密な物語と社会との接点を紡ぐ鍵として、スマートフォンのヴォイス・メモをそのまま使ったかのような荒い録音の「声」を引用してきたように思う。
ひるがえって、『球体』のハイファイさは、寓話的で壮大なスケールの物語を展開する本作の特徴を反映している。音響が、ひとつの世界を丹念に構築するために研ぎ澄まされているのだ。
"円環"や"テレパシー"、そして"球体"のハイライトと言うべき"世界"にみられる、80年代の王道をゆくポップスを彷彿とさせるPCM系のドラムマシーンやきらびやかなシンセサイザーの音色も、本作を特徴づけるサウンドだ。しかし、ノスタルジーを喚起するギミックや、80年代という時代そのものへの憧憬は感じさせず、あくまでもクールに響かせている点がおもしろい。Nao’ymtによる過去のプロデュース作を聴いてみると、80年代のブラック・コンテンポラリーを思わせる音使いをアップデートする本作の萌芽が、節々に見受けられるのも興味深い。
アコースティック・ギターとヴォーカルというシンプルな構成から一転、アップテンポなエイトビートのシンセポップに変化する「テレパシー」にせよ、あまりにもドラマチックなバラード調のトラックのうえで、三浦が存分にヴォーカル・スキルを見せつける「世界」にせよ、ともすれば仰々しくキッチュに陥りかねないところを、的確な音色選びと解像度の高いプロダクションによって、クールさを湛えつつもストレートにこころ揺さぶるポップスに昇華されている。
加えて言えば、三浦の近年の活動を考えれば当然のことながら、『球体』は、フューチャー・ベースをはじめとしたEDM以降のダンス・ミュージックも貪欲に取り入れている。その点で本作の白眉というべきは、"飛行船"だ。ドロップに向かってゆっくりとビルドアップしてゆく高揚感と三浦の歌唱が見事に調和していることはもちろん、終盤にだけ訪れる16小節の激しく複雑なビートの展開は、先鋭的なダンス・ミュージックの様式を取り入れながらも、その機能性(=ミックスしやすさ、踊りやすさ)からは距離を取る絶妙なバランス感覚を見せている。
ダンス・ミュージックとの距離感という文脈で言えば、パフォーマンスとしての『球体』を見たときに意外に思えたのは、いかにもダンスのスキルを披露するにふさわしそうな、アップリフティングなビートがあらわれる箇所がむしろ、物語的なクライマックスを表現するために用いられていたことだ。"飛行船"の話を続けると、パフォーマンスにおいて三浦は、尺八のような音色をフィーチャーしたドロップでは華麗なステップを披露する一方で、もっとも激しくビートが躍動する終盤の16小節ではステップを止め、舞台上の飛行船のなかへと姿を消す。深読みにすぎるかもしれないが、スキルの誇示ではなく、見せたい世界の表現に専念する三浦の考えをそこに感じた。
ここまでもっぱらサウンド面の話題に終始してきたが、ソングライティングの観点から言っても、『球体』が達成しているクオリティは注目に値する。作品の提示する世界を表現するために注意深く選ばれた語彙や、丹念に構成された韻もさることながら、注目したいのは譜割り、フロウだ。
アメリカを中心に、ポップスにEDMやトラップのサウンドが取り入れられることが当たり前になったことで、歌のリズムのあり方も変化している。もっともわかりやすい例を挙げれば、トラップが浸透してからというもの頻繁に耳にするようになった三連符を多用した譜割りは、ラップミュージックの範疇を超えてポップスの領域においても基礎的なボキャブラリーとなりつつある。しかしながら、トラップ的な三連は、ことJ-POPにおいてはまだまだ一般的とは言い難い。同じアジアのポップスであっても、K-POPがこうしたリズム感覚の変化を柔軟に取り入れているのとは対照的だ。
この点において、『球体』に収められた楽曲のところどころに顔を出す、きわめて現代的なリズム感覚を反映した譜割りは、2018年現在のJ-POPでは類例の少ない、高い完成度を誇っている。それが最も如実にあらわれているのは、"綴化"だろう。
アタックの強い硬質なキックにそえられたサブベース。鋭い緩急のついたハイハット。少し曇りがかったようなパッド・サウンド。トラップのマナーを踏襲したサウンドに乗る三浦大知のヴォーカルは、ビートにあわせた独特な譜割りを乗りこなしつつ、明晰な発声で日本語としての詩情を充分に感じさせる。とりわけ、三連符を基調に展開するサビは、大胆なシンコペーションを挟んで、パーカッシヴな響きと言葉の意味がぎりぎりでせめぎ合っている。こうした最先端のリズム感覚と日本語詞の見事な融合は、三浦の高いヴォーカル・スキルがあってこそ挑戦できる領域だ。
『球体』- ポップ・ミュージックの傑作
最後に、『球体』が類稀であるのは、サウンドやソングライティング、そしてダンスパフォーマンスで達成したクオリティの高さと、その作品全体が提示する世界が両立している点にある。つまるところ、音楽としての、パフォーマンスとしての洗練が、表現しようとするコンセプトへと捧げられているのだ。その意味で、『球体』というきわめて抽象的な概念がタイトルに据えられているのは、アーティストが自己表現や自己実現のためにプライヴェートな物語を紡ぐと言うよりは、表現の限界に挑むことで普遍的な物語を描き出そうとする、その姿勢のあらわれであるように思える。
三浦大知とNao’ymtが練り上げた具体的なコンセプトがいかなるものなのかは、作品中では明言されないから、あくまで各々がどのような要素に着目して、どのように読解するかに委ねられている。とはいえ、詞や舞台演出のなかに一貫して現れる「水」のモチーフや、『球体』というタイトル、都市から海、森林、砂漠までを行き来する演出は、この作品が描こうとするものが、地球そのもの、そして地球上を旅し続ける人間の姿であることを示唆する。また、イントロとアウトロが一致する構成(波の音からはじまり、波の音で終わる/アパートらしき一室からはじまり、同じ部屋に帰ってゆく)は、この作品が提示する物語が直線的な構造を持たず、むしろ円環であることを強調している。それはまさにこの作品が、語り終わることのない普遍的な寓話を語ろうとしていることの証左だ。
ポップ・アクトの使命は、「観客を楽しませる」という一点に集約されると言っていいだろう。そう素朴に考えたとき、三浦大知の『球体』というプロジェクトは、いささかハイブロウ気味に感じられるかもしれない。じっさい、キャッチーなことばを排し、あえて多くを語らずに意味の余白を残した楽曲にせよ、抽象的なアルバムタイトルにせよ、ポップ・ミュージックならではの易しさや親しみやすさからは少し距離を置いている印象がある。しかし、『球体』収録曲を一聴すればわかるとおり、妥協のないプロダクションや、圧倒的なスキルで披露される歌唱には、理解や共感を超えて感情をゆさぶる表現の力が宿っている。
矛盾するようだが、こうした、極限まで洗練された表現が普遍的な感動をもたらすという経験もまた、ポップスの世界に特有のものである。しばしばポップスに携わる作曲家や編曲家といった人びとが尊敬の意をこめて「職人」と呼ばれることからわかるように、現代のポップスの原理は分業的なプロフェッショナリズムであって、ひとつの表現をともに練り上げていくコラボレーションの美学を持っている。商業主義の権化として批判の的とされることも珍しくはないこの原理は、それでもなお私たちを魅了するコンテンツを生み出し続けている。
『球体』もまたそのひとつだ。この作品は「ポップ・アクトがアーティスティックな表現に挑んだ意欲作」などではなく、三浦大知とNao’ymtというふたりの職人が、ポップスのプロフェッショナリズムの側面を極限まで追及した、まぎれもない「ポップ・ミュージックの傑作」なのだ。
Info
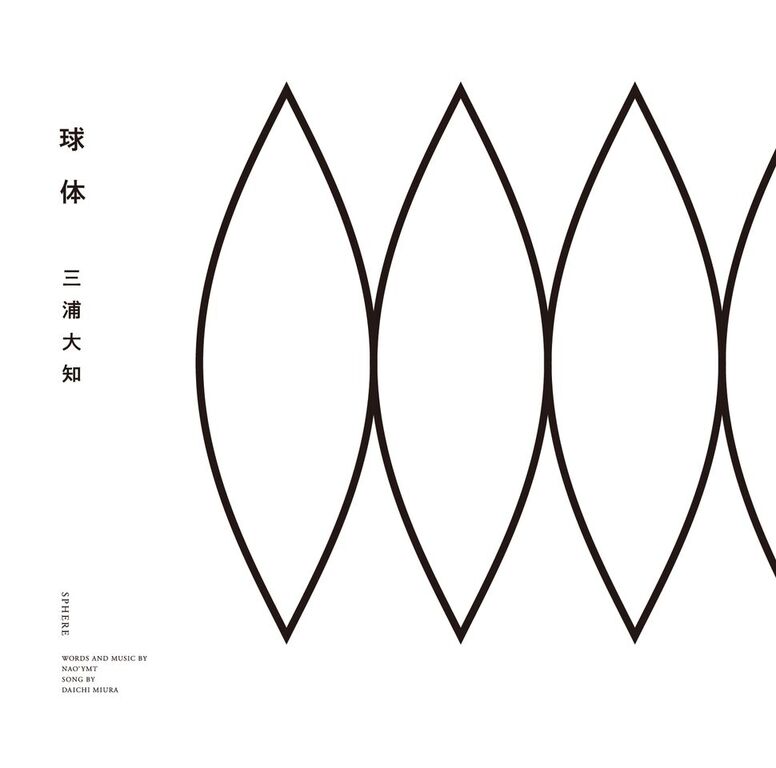
三浦大知 - 『球体』

