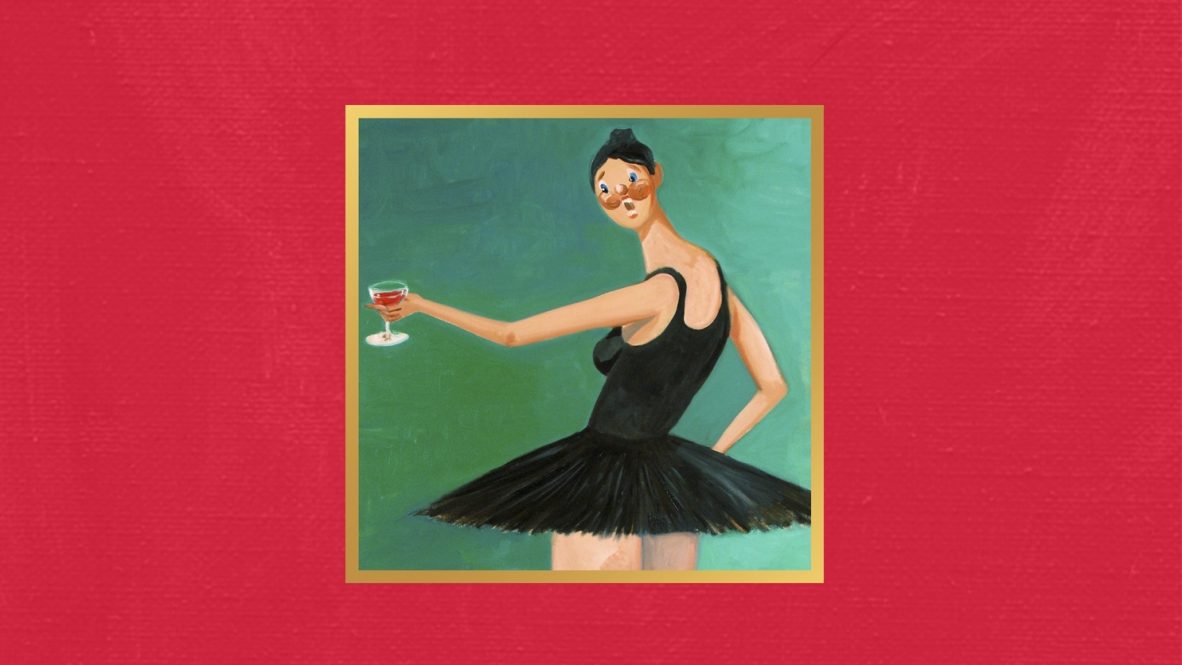Kanye Westのキャリアや作品、人物像に迫る書籍『カニエ・ウェスト論――《マイ・ビューティフル・ダーク・ツイステッド・ファンタジー》から読み解く奇才の肖像』が、DU BOOKSから6月8日に邦訳・刊行される。
本書は代表作『My Beautiful Dark Twisted Fantasy』を題材に、Kanye Westのナルシシスティックな人物像や彼の生み出す作品をひも解くもの。もちろん『College Dropout』『808s & Heartbreak』『Yeezus』などその他の重要アルバムについても詳しく解説しているほか、日本語版には本書の翻訳を手がけるライターの池城美菜子による解説を追加収録。さらに、現時点までの全キャリアを総括した巻末付録「カニエ・ウェスト年表」も掲載される。
今回FNMNLでは、本書から「贖罪のアート」という章の全文を独占公開。こちらを読んで興味を持った方は、是非書籍をチェックしてみてほしい。
贖罪のアート
自分は誤解されている、とすっかり思い込んでいるようだが、この10年間を通して、カニエ・ウェストはほとんどのアーティストが受ける一生分以上の強い称賛を得ている。耳をふさぎたくなるほど派手に宣伝した6枚目の《Yeezus》(2013年)のリリースにあたって、ニューヨーク・タイムズ紙は日曜日のアートセクションの表紙に彼の写真とインタビュー「カニエの仮面の裏側」を掲載した。
ライターのジョン・カラマニカは3日に渡ってインタビューし、音楽以外の漠然とした野望やキャリアをめぐる物語、エレクトリックで虚無的なアウトバーンを寒々と走り抜ける、カニエが表現するところの「野心的なミニマリズム」である《Yeezus》が示す新しい方向性を聞きだしている。カラマニカのすばらしいイントロダクションには、こう記されている。
「ヒップホップにありがちなナルシシズム的な欲求と社会的利益との矛盾を、彼ほど完璧に具現化したラッパーはいないし、彼ほど豊かさを華麗に祝ったプロデューサーもいない。キャリアを通して過剰モードを貫き、いかに神々しく、思考が感化されるような、スケールの大きい音楽をどう作るか苦心してきた。また、彼は中産階級の価値でもハイファッションでもハイアートの夢でも、ジャンルそのものの門戸を開いた」
《MBDTF》制作時の裏にあった衝動に話がおよぶと、このインタビューは俄然おもしろくなった。カニエはこのアルバムを、一度自分から離れてしまったオーディエンスのCD棚に戻るための「長い、バックハンドで出した謝罪」だと表現したのだ。「みんながほしがっていたアルバムを作ってみた」とも言った。カラマニカは、次の質問で切り返す。「とすると、《Dark Fantasy》は不誠実なアルバムにならないですか?」。それに対して、カニエはどんなに先見の明のある人(ヴィジョナリー)でも妥協は避けられないと言ってみたり、暗に自分とスティーブ・ジョブスを比べてみたりして、ずいぶんと尊大な考えを述べたあと、最終的に《MBDTF》は彼の「決して満足できない」性癖の例として妥協したレコードだと言い切った。
キャリアを通して、彼のペルソナのもっとも魅力的で、かつぞっとする部分は彼の二重のエゴ――その動きひとつひとつに子どもみたいな魅力と嫌悪感が奇妙に入り混じるところである。2005年のハリケーン・カトリーナ救援テレソンの際に大炎上した彼の映像を見ると、彼の声が地震計なみに震えていることに気がつく。彼が成し遂げたかったことはただひとつ、ニューオーリンズで漂っている死骸と漂積物、人々の怒りをも一手に引き受け、正義感による憤りへと急速注入でぶち込み、それをリビングルームにいる無知で無関心な大衆へ震える声で勢いよくぶちまけることだった。彼のやり方は、ほかの人とは違うのだ。私たちが目にしたのは、政治的な勇気を奮った早熟のポップスターではなく、こちらが恥ずかしくなるほど言葉足らずの、しかしながらショッピングに対する罪悪感などではなく、人種的な不平等とアメリカで固定されている最下層の階級について意義のあることを必死で訴えようとする彼の姿だった。自分で正当化した善意を無謀な方法で伝えるという緊張感こそ、カニエの人生と音楽の活力源だ。だからこそ、ビート作りの匠、ラップの天才としてのステータスがありながら、彼の名前は刺激的で装飾的なラップのフューチャリズムの大家としてではなく、テレビの生放送中におきた、みんなが知っているふたつの炎上事件によって、アメリカの多種多様な一般大衆に知られている。ひとつめは前述した「ブッシュ・プッシュ」事件で、彼はだれにも頼まれていないのに現職の大統領に向かって、いきなり言葉のパンチを浴びせた。
ふたつめはもちろん、2009年のMTVヴィデオ・ミュージック・アワードでの、テイラー・スウィフトの受賞スピーチへの道化じみた乱入事件だ。彼の意図は、自分で公言したとおり、このときも善意から出ていた。つまり、彼はスウィフトに当たっていたスポットライトを、本来、受賞するべきだったほかの人(ビヨンセ)のために奪ったのだ。「そのときの彼の行為はポップ界の大方の意見を代弁していた」「無味乾燥なアワード・ショウを解体してみせた」「彼はあれであった、これであった」などなど、この行為ははるか彼方まで拡大解釈された。テイラー・スウィフトは市場において侵してはならない聖域であり、何百万、何千万もの世界中の10歳前後のトゥイーンやティーン、20代の人々の自尊心を商品化した大海そのものだった。彼の暴挙は壮観なまでにはっきりとわかる自己破壊であり、それさえなければ平凡だったはず場面を剥奪したことによって、彼は全世代の女性に嫌われてしまったかもしれないのだ。もともと彼の音楽を品がないと思っていた人たちは、彼の異常なふるまいはその音楽自体がナルシシスティックな道化による戯言、クールエイドを飲んで自家中毒になった子どもが発する不愉快な喘鳴(ぜんめい)だと決めつけた。彼の評判は無作法な人種への悪口から有名人の思い上がりとまで言われ、さまざまな苦情の種となって広がった。世界中の人々がコンピュータで彼の写真を関係ない写真に重ねて、「あとで最後まで話させてあげるから、でもさ……」という悪名高い横槍の変形を字幕にしたミームがネットを駆け巡ったときに、彼の有名人としての人生は最悪のときを迎えた。その前の8月に、保険制度の改革をめぐって全国の市議会が血みどろの対立をしていたこともあり、アメリカ人はカニエの行動への嫌悪感を共有することで盛り上がった。この出来事の数日後、〔テレビホストの〕ジェイ・レノの前でカニエがキリストになりそこなった瞬間を見るにつけ、悔恨だけでは償いきれないことがわかる。必要なのは、奇跡だった。
精神的に彷徨ったどの詩人よりも、ダンテは「事が収まるまで時間をとる」ことについて、もっともエレガントで根本的な理由を世界へ残している。「人生という旅の途中で/森の暗闇に紛れ込んでしまった/前に続くまっすぐな道は消えてしまった」。気まぐれで謎の多い『マッドメン』の主人公、ドン・ドレイパーでさえ、第6シーズンでは浜辺に佇んで、この『神曲』地獄篇の第1節を反芻していた。当然ではないか? 人間とはなにか、という教理問答の答えは、何世紀ものあいだ混沌のなかを漂い、人間はまちがいを冒す多感な生き物というイメージのままだったのだから。壮大なこじつけへの抑えがないほどの欲望、まっすぐな道から自ら外れることにかけてのはっきりした才能を考えると、ダンテが描いた漂流者のイメージは、2009年のスウィフト大災害後のカニエの状況にぴったりあてはまる。
コンプレックス誌の編集長、ノア・キャラハン・ビーヴァーはここ数年、カニエの心の友であった。その彼を、カニエは2010年の頭に《MBDTF》を制作していたオアフ島のエイヴェックス・ホノルル・スタジオに招いている。2002年にマス・アピール誌に彼が書いた予言的な文章で(そこで彼はカニエを「本物の不良を魅了できるくらいヒップホップ的で、アンダーグラウンド好きが共感できるくらい思慮深い」と書いている)、キャラハン・ビーヴァーは文化的な生態系にカニエの軌道を描き入れ、逸話を通して彼の不可解な精神状態を覗き込んでみせた。2010年のコンプレックス誌11月の巻頭特集「プロジェクト・ランウェイ」で、私たちの時代でもっとも大胆なポップスターがマグナム級の作品に取りかかるときに、絶対に必要だったプロセスの目撃証言を書いている。
2009年の10月中旬にカニエからかかってきた電話について、彼はこう書いている。「カニエ・ウェストは、もう終わりだ、と言った。音楽にうんざりしているのだ。彼には明らかに休みが必要で、無意識に次の取り組みを用意していた。いま、彼はファッションに夢中だ。赤いレザージャケット、金の装飾、90年代後半のヒップホップの退廃的なファッションを落とし込んだデザイン。あまりに彼が興奮していたため、私はやった方がいいと励ましたが、完全に音楽を辞めてしまうのはもったいないと本音も言った」。カニエはレノの番組に出演したあと、国を離れてミラノから電話をしていた。彼は日本で数週間を過ごしてからローマに飛び、そこでイタリアのファッションブランド、フェンディでインターンを始めた。ローリング・ストーンズのもっともすばらしいLP、《Exile on Main Street》が南フランスで制作された状況を引用しながら、キャラハン・ビーヴァーは海外で活躍するカニエの可能性について興味をそそられたと認めている。直接やりとりをしないないまま、数ヶ月後に彼は国外に駐在していたラッパーから短いメールを受け取った。「ヨーーーー、ファミリー、あけましておめでとう。新しい音楽を聴かせるのが待ちきれないよ!」。3月の終わり、キャラハン・ビーヴァーは「カニエが(4枚目のアルバムである)《808’s〔& Heartbreak〕》を録音した海辺にあるエイヴェックス・ホノルル・スタジオにいて」、カニエは「24時間3つのセッション・ルームを」新作の完成に満足するまで一棟ごと占領していた。
ノア・キャラハン・ビーヴァーの記事を読む楽しみは、アルバム制作のプロセスと、そこに織り込まれた利害関係を明晰な視線で描写している点にある。彼はカニエの計画の軽い躁っぽいリズムを、事実として淡々と書いている。
「カニエはラップトップを見つめ、メールとブラウザの上に開いた15のアートの参照記事を行ったり来たりしている。彼は自分のブログにそれらを引用する場合、どこまでリスクを冒せるか推しはかりながら、ときどきエンジニアに向かってあれこれ注文を吼えたて、ビートの些細なパートを調整する。そのあいだ、彼はコンピュータの画面から一切、目を離さない。これが彼の作業の仕方なのだ。まったくもって典型的なADD(注意欠陥障害)」
アルバムを聴いた人間なら、この文章には驚かないだろう。 あの作品は、美的に変形した躁病のエネルギー以外のなにものでもないのだから。「私がハワイに滞在した5日間のあいだ」とキャラハン・ビーヴァーは続ける。「カニエは家どころかベッドでも一睡もしなかった。彼はスタジオの椅子かソファでたまに90分の集中した昼寝を取り、一晩中作業した。エンジニアたちは24時間体制で卓の前にいた」。さらに興味深いのは、ビーヴァーが制作に関わった人たちの共通認識を記していることだ。
「私たちが話すことといえば、カニエのアルバムについてばかりだった――どういう意味をもつのか、なにを達成すべきなのか。ビートやライムの先にある核に、私たちがテレビドラマの『ロスト』さながらにこの島に招集された理由があった。はっきりと話し合われたことはないが、カニエが罪を償う鍵は、いい音楽を作ることにあると全員がわかっていた。適切な曲が収められた適切なアルバムで、すべての論議に打ち勝つこと。われわれはそのために力を貸し、挑戦し、触発し合うのだ」
アルバムに参加した時期をさして、彼がおもしろおかしく名づけた「ラップキャンプ」へ自分が参加したことに対し、キャラハン・ビーヴァーは控えめな驚きを記している。ラップを先導する人々によるこの実地講座を、キャンプへの参加に例えたのは理に適っている。《MBDTF》に参加したアーティスト、プロデューサー、エンジニアを精査してみると、クレジットは映画なみの長さになるのだ。その制作された範囲の広さと過剰なほどの熱量を聴いたあとに鮮明に描かれたイメージは、音を超越してまごうことなき視覚に訴える側面がある。《MBDTF》はさまざまな側面からヴィジュアル・アートのようにも感じられるのだ。制作現場での繊細な共同作業の様子を知れば知るほど、カニエは監督であり、曲の作者でもあるように感じてしまう。この考えをより理解するために、キャラハン・ビーヴァーはハワイのラップキャンプに参加した、レジェンド級のヒップホップ・プロデューサー、Qティップの言葉を引用している。
「芸術作品において、ミケランジェロやレンブラントとかいった大御所はみんななにかしらスケッチをしているが、その手で描いたとはかぎらない。ダミアン・ハーストがコンセプトを打ち立てたら、大勢のクルーが作業員のようにそれを仕上げるんだ。彼の手はキャンバスに触れる必要はないが、その考えは反映される。カニエもそうだ。彼はビートやライムが浮かんだら、われわれ全員に提示する。俺たちは彼が始めた音を詳しく吟味し、さらに引き裂いてみたりなにかを足したりする。セッションの終わりには、みんなで力を合わせて作ったものを彼がまとめ、変化させると、全体はパートごとよりずっとすばらしいものになる。彼は本物の魔法使いだ。実際、彼が行っているのは錬金術なんだ」
つまり、まだ埃をかぶっていたカニエの神がかったヴィジョナリーとしてのアイディアは、巨匠たちが実際に絵筆を握らず、まわりに託して最後にまとめた美術品と同じレベルだとQティップは言っているのだ。パッと思い浮かぶのは、アンディ・ウォーホールのファクトリーやスティーブ・ジョブスのアップルである。この点から照らし合わせると、カニエが自分からジョブスを引き合いにだしたのは、それほど的外れではない。ジョブス個人の天賦の才は創造的なアートから、テクノロジー、商売にまで多岐にわたり、表面上は必然性がないように見えるバラバラな要素をまとめて、卓越した美しさをもつ製品に落とし込むと同時に、市場で他社製品を駆逐した。iPodは初めて発売された持ち運びができるMP3プレイヤーではないが、美術品も兼ねていた製品としては史上初だった。そのクリーンなデザイン、なめらかで美的なつやは、音楽を聴く「行為」を「経験」に変えてみせるという抗いがたい保証つきだった。私たちは、毎日さまざまなデバイスを使うたび、ジョブスの思想がキャンバスの隅々にまで広がった輝かしいアイコンをいくつも目にする。ジョブス同様、カニエは自分の美的感覚を完全に信じている。彼のプロダクションは常に性格(エートス)として、狂乱したコラージュであり、彼自身の存在を賭けて、自分が目をつけたものならなんでも――過去のポップミュージックでも、現代美術でも、オートクチュールでも――改造できる(そして、リブランドできる)という創造的なナルシシズムの示威行為なのだ(2013年の《Yeezus》ツアーでは、コンサートの途中で、それらを自分の「夢の数々」とわめき散らしていた)。
アートフォームとしてのコラージュはもちろん、矛盾をふくんだ文章ですでに定義づけられている。1912年、ピカソは「籐椅子のある静物画」でキャンバスにオイルクロスを糊づけし、実物の長いロープで楕円形の作品をふちどった。絵画の境界線を越え、毎日の生活から本来は相容れないような性質の異なるものをサンプリングしたことで、ピカソは画材の可能性を広げたのだ。ダダイズムやキュービズムの全盛期からさらに進化して、優秀なコラージストたちは工場から出た岩くず、留守電メッセージ、ATMの防犯カメラの映像といったさまざまな素材を使って、芸術が内包するアイディアの不連続性を映しだした。コラージュを通して、芸術家たちはありふれた課題やプログラム化された手法からなんとか逃れようとし、まだ発見されていない直覚的な可能性へと自らを開放する。相容れない“外国の”素材を芸術作品へ輸入するのは、この角度から照らしてみると分裂というよりも修正の意味合いが強い――単調な予定調和、見せかけの世界の蜃気楼のなかでまどろむのも必要なことだが、そこから見える幻影は限定されてしまう。コラージストが個々の活動で選び抜き、流用した、混沌のなかに刻まれたとらえどころのないパターンや、ノイズに埋められたハーモニーだけを通して、私たちは探していたことさえ気がついていなかったものを見つけるのだ。断片化と反啓蒙主義を讃えるこのモード以上に、21世紀の生活と符号するアートフォームはほかにあるだろうか? 《MBDTF》は、美しく生まれ変わる前提条件はあらゆる種類の断続性にあるというアイディアを、心の底から叫ぶかのように取り込んでいる作品なのである。
(翻訳:池城美菜子)
注釈
・アジット・ポップ:「アジテーション・ポップ」の略称。政治理念や意見を述べた音楽。
・ウェス・アンダーソン:独特の色彩感覚と世界観で人気のアメリカの映画監督。スティーヴ・ズィスーはウェスの映画『ライフ・アクアティック』の主人公。
・マッドメン:2007年から2015年まで放映された、1960年代の広告業界を舞台にしたドラマ。緻密なストーリーとキャラクター設定で高い評価を得た。おもしろいが、とても疲れるドラマである。
・ロスト:2004年から2010年まで放映され、大人気を博したドラマ。飛行機が墜落して漂着した島での群像劇。真田広之が重要な役どころを演じた。
INFO
『カニエ・ウェスト論――《マイ・ビューティフル・ダーク・ツイステッド・ファンタジー》から読み解く奇才の肖像』(仮)
カーク・ウォーカー・グレイヴス 著 池城美菜子 訳・解説
予価1,800円+税
四六/並製/256頁予定
6月8日(土)発売予定